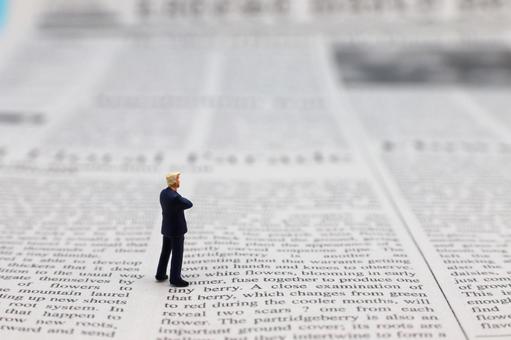
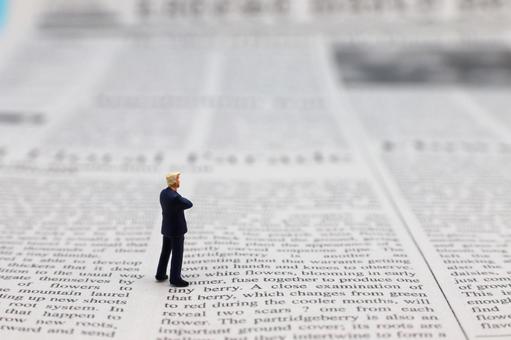
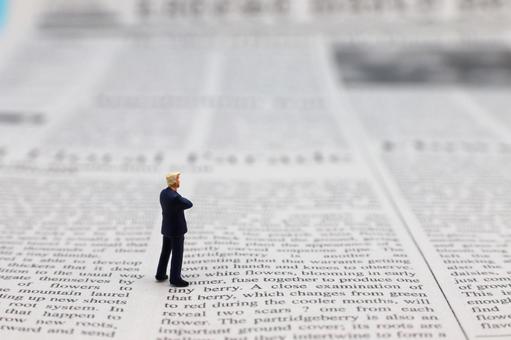
10年の進化って凄いと同時に…

SAAT NETIZENにご用心
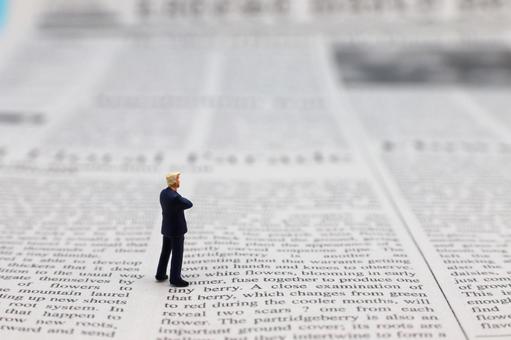

センサーを含めた計装機器から信号をもらう時は4-20mAなり1-5Vで受け取りますが、経験上は4-20mAの方が多いと感じています。測定する時は配線を外すなどの手間がかかりますが、最近では外さなくても測れるテスターやクランプメータなども発売されているようですね。減衰が少ないというメリットもあります。いざとなれば250Ωの精密抵抗を加えることで1-5Vに変換も出来ますしね。
PLCではこの信号をアナログ入力ユニットを使って受け取ります。ユニットの解像度特性で20mAの時の値が32000であったり、16000であったり4000に変化します。この辺はメーカーや機種によって多種多様ですね。PLC業界だと当たり前の数値ですがIT屋さんだと32767では無いんですか?となったりするのが厄介ですが…
さらに4mAの時の設定をどうするのかはお客様の考え方によって変わってきます。
三菱電機のR64AD-GHを例に取るとパラメータを「4-20mA」で設定すると0~32000の範囲でAD値が変化します。これを「0-20mA」にすると同様に0~32000なのですが有効範囲が限られて6400~32000の範囲でAD値を採用するようになります。
前者の方はFA系でよく採用されているような気がします。1ビットの重みをより細分化出来るメリットがあります。後者は公共系でよく採用されているような気がします。重みよりも断線した際に6400以下となるのでそれを使って配線の断線警報を出す用途に使われていたりします。
一昔前は断線検出機能が無かった(あったけど使われていなかった?)ので私自身は後者のそれを使っていますが、最近の機種は断線検出機能が装備されているので考え方を変えていく必要があると思っています。