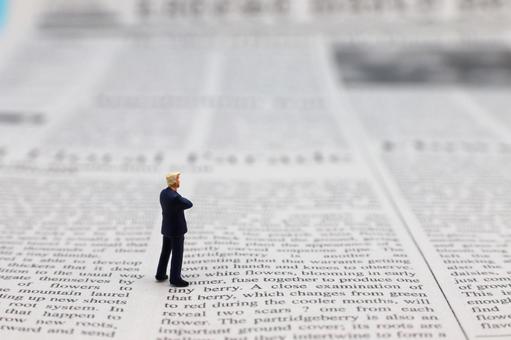
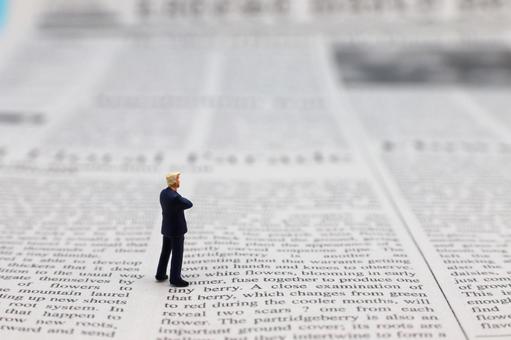
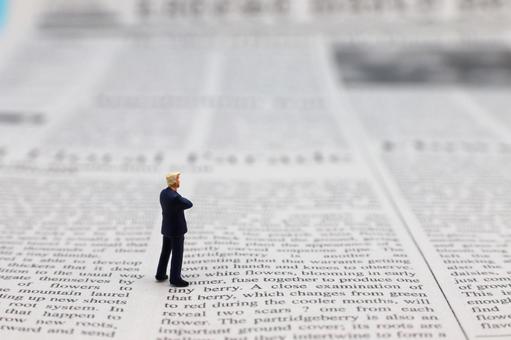
10年の進化って凄いと同時に…

SAAT NETIZENにご用心
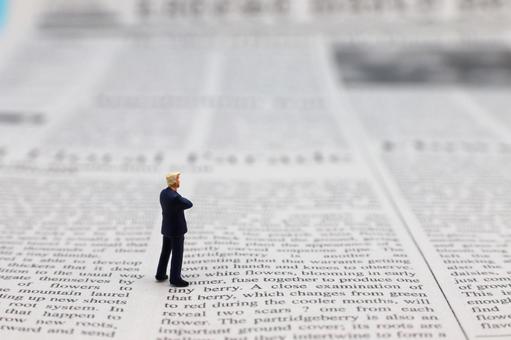

SNSで目にした言葉が頭から離れません。『ラダーを使えるスキルに価値が無くなる』という一節…某たろうさんは「制御プログラムはダウンロードして使う時代になる」と仰っていました。BECKHOFFも制御盤をモジュール化した『MX-System』を発表しています。
このようなシステムが当たり前になってくると負荷制御も組み込みになってくるような予感がしてなりません。例えばポンプ2台の交互制御等のスタンダードなものはポンプ自体にコントローラを組み込んだ製品が出てきたり、空調機器の台数制御等も専用コントローラを持つようになるのかもしれません。
中央管理された司令室からコマンドを叩くと通信ネットワークに乗ってコントローラに届きそこで制御設定が完了してしまうのが当たり前になった時、ラダー屋さんの存在意義は皆無に等しくなるでしょう。
三菱電機iQ-Rシリーズはメーカーからファンクションブロックをダウンロードして実装できるようになっています。KEYENCEも今のままではないでしょう。『KV-10000』シリーズがリリースされるかもしれません。その時はIEC規格に乗ってくるのではないかと予想します。他のメーカーも足並みを揃えてくるでしょう。ファンクションをつなぎ合わせればある程度の事が出来てしまうと、私を含めてある程度の事しか出来ないラダー屋さんを使うという選択肢は限りなく低くなります。
通信に関しても規格が固まりFL-Netのようにパラメータを設定してしまえばあとはコネクタを差し込めば(無線かもしれませんが)繋がるようになってくるのではないかと感じています。今はそのパラメータ設定が難しいかもしれませんがウィザードにそってポチポチやっていけばパラメータが出来上がる仕組みも出来上がってるかもしれません。
ロボットにしても専門の知識を持った方がプログラムを組み、ティーチングを行っていますが産業用の大きなロボットでも協働ロボットのようにダイレクトティーチングが出来るようになりNode-REDのようなプログラミングツールが装備されるかもしれません。
我々が本領を発揮できる『現地調整』も予めCADツールやプラントシミュレータなどで試験調整を行うことによりニーズは無くなっていくのかもしれません。実際にCADでPLCラダーを連動させていたり、工場設備をPLCと連動させてシミュレーションを行う製品は世の中に出てきています。
そのような時代はもう目と鼻の先まで来ています。数年前には思いもつかなかったことが現実に動いていることを鑑みて今後の行動を今一度考え直そうと思います。